
TRONWARE Vol.212
ISBN 978-4-89362-389-8
A4変型判 並製/PDF版電子書籍(PDF版)
2025年4月15日発売
読者アンケート
読者の皆様のご意見を記事作りの参考にしたく、 取り上げるテーマのご希望やご意見をぜひお聞かせください。
➔ご回答フォーム
特集1:公共交通オープンデータチャレンジ2024 最終審査会・表彰式
「公共交通オープンデータチャレンジ2024 – powered by Project LINKS -」は、公共交通オープンデータを活用した、オープンイノベーションのためのアプリケーションコンテストである。公共交通オープンデータ協議会(ODPT)は2017 年より「東京公共交通オープンデータチャレンジ」というアプリケーションコンテストを4回にわたり開催し、東京オリンピック・パラリンピックを控えた「東京」を舞台に、一般の開発者からのアイデアやアプリケーションを募集した。これらを通算して5回目の開催となる本コンテストは、2024年7月から開始され、国内外から約500件の応募があった。
その最終審査会・表彰式が2025年2月15日に東洋大学赤羽台キャンパスのINIADホールで開催された。ソフトウェアエンジニア兼タレントの池澤あやか氏の司会のもと、主催者を代表してODPT会長で東京大学名誉教授の坂村健審査員長と、国土交通省 総合政策局 モビリティサービス推進課/情報政策課 総括課長補佐 Project LINKSテクニカル・ディレクターの内山裕弥氏が挨拶を行った。
続いて、17組のファイナリストによるプレゼンテーションが行われた。短い持ち時間の中で、各組が公共交通データを活用した革新的なアプリケーションやサービスを発表した。
書類審査と最終審査のプレゼンテーションをふまえ、6名の審査員による厳正なる審査の結果、最優秀賞1作品、準最優秀賞2作品、優秀賞4作品、審査員特別賞4作品が発表された。また、このほかに特別賞として東日本旅客鉄道賞(JR東日本賞)、Project LINKS賞、INIAD賞が授与された。
審査員による講評では、坂村審査員長をはじめとした審査員から各受賞作品への評価と今後の展望についてコメントが寄せられた。特に、オープンデータ活用の進展と参加者の技術的成長が高く評価され、次回のコンテスト開催に向けて期待する声が多く上がった。
- 「公共交通オープンデータチャレンジ2024 – powered by Project LINKS –」結果発表
https://challenge2024.odpt.org/award/

特集2:TRONプログラミングコンテスト2025 誌上セミナー
トロンフォーラム(会長:坂村健・東京大学名誉教授)は、2025年1月21日(火)より、「TRONプログラミングコンテスト2025」を開催している。本コンテストは、国内外の技術者および学生を対象とし、世界標準であるTRONのリアルタイムOS「μT-Kernel 3.0」を用いたマイコンのアプリケーション、ミドルウェア、開発環境、そしてツールなどの各分野で競うものである。
今回のテーマは「TRON×AI AIの活用」。AI技術を取り入れた革新的な作品が期待されている。
本コンテストではSTマイクロエレクトロニクス株式会社、ルネサス エレクトロニクス株式会社、インフィニオン テクノロジーズ ジャパン株式会社、パーソナルメディア株式会社の協力のもと、応募者には選考のうえ、μT-Kernel 3.0を搭載した最新のマイコンボードが提供される。
本特集では、本コンテストの概要と各マイコンメーカーのマイコンボードに対して提供されているμT-Kernel 3.0 BSP2について紹介する。また、2025年2月に開催された各マイコンメーカーによるウェビナーの内容を誌上セミナーとして再構成して掲載するほか、2024年のコンテスト入賞者に応募から作品提出までの体験記を寄稿していただいた。
コンテストの参加エントリー期間は2025年4月30日まで。ぜひ本特集を参考にしていただき、チャレンジしていただきたい。
- TRONプログラミングコンテスト2025
https://www.tron.org/ja/programming_contest-2025/
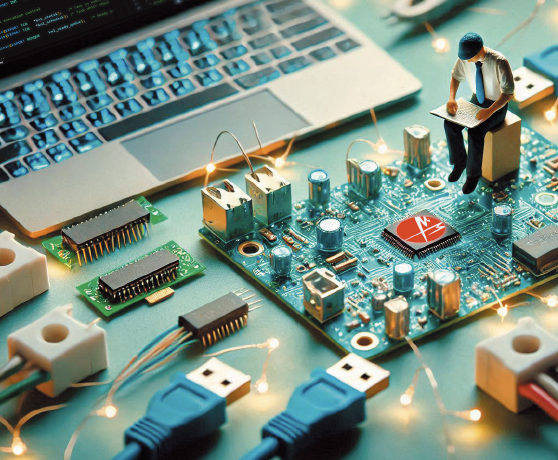
第2回 歩行空間DX研究会シンポジウム
国土交通省は「人・ロボットの移動円滑化のための歩行空間DX 研究会」(以下、歩行空間DX研究会)の活動として、「第2回 歩行空間DX研究会シンポジウム」を2025年1月23日に東洋大学赤羽台キャンパスINIADホールで開催した。本研究会は、人やロボットが円滑に移動できる環境をより早期に実現することを目指して2023年6月に発足した。最新の技術や研究事業、取り組みなどに関する情報共有や意見交換を行うことを目的としている。本研究会の顧問には、「ICTを活用した歩行者移動支援の普及促進検討委員会」の委員長である坂村健INIAD cHUB(東洋大学情報連携学 学術実業連携機構)機構長が就いている。
シンポジウムの第1部では国土交通省 政策統括官の小善真司氏による開会挨拶の後、坂村機構長による歩行空間DX研究会のプロジェクトの主旨説明と、歩行空間の移動円滑化データワーキンググループおよび歩行空間の3次元地図ワーキンググループの取り組みが各座長から紹介された。
第2部のパネルディスカッションは「持続可能な移動支援サービスの普及・展開に向けて」をテーマとし、有識者、民間事業者、行政などから関係者が登壇し、闊達な意見交換と情報共有が行われた。

TIVAC Information:PCアプリケーションでのSBOM利用
SBOM(Software Bill of Materials)は、ソフトウェアを構成するすべてのコンポーネントや依存関係をリスト化したソフトウェアの部品表のことだ。ソフトウェア部品を可視化することで既知の脆弱性を迅速に特定・対処できるため、セキュリティリスクの低減と安全性の向上に有効であるが、組込みシステム開発ではまだ一般的ではない。意識の高いユーザから要求があれば提供される可能性はあるが、開発者にとっては負担に感じることが多いようだ。
一方、PCアプリケーションでのSBOMの利用は広まっており、開発者が用意した環境記述ファイルが、そのままSBOMの代用品として使えるようになっている。つまり、わざわざSBOMを作るのではなく、既存のファイルが流用できるようになっている。本稿では、ソフトウェア開発においてビルド、テスト、デプロイメントなどの工程を自動化して継続的に行う手法である「CI/CD」と、セキュリティリスクを可視化するツール「trivy」について説明する。

From the Project Leader
プロジェクトリーダから
今号は、トロンフォーラムが主催する「TRONプログラミングコンテスト2025」と、公共交通オープンデータ協議会(ODPT)と国土交通省が主催した「公共交通オープンデータチャレンジ2024 – powered by Project LINKS -」を、2大特集として大きく取り上げた。
これらは、対象としている分野はまったく異なるが、コンテストという点で共通している。私はコンテストという手法がオープンアーキテクチャを進めるために非常に重要であると思っている。コンテストに参加するにはまずその対象とするものをよく理解する必要がある。TRONプログラミングコンテストであれば、μT-Kernel 3.0という最新のリアルタイムOSに対しての理解だけでなく、そのOSを搭載している最新のマイクロコンピュータに関しての知識も必要になる。また、公共交通オープンデータのコンテストに参加するには、ODPTが提供するオープンデータのしくみや使い方などを理解していないとデータを扱うこともできないので、応募するにはそうした基本的な理解をまず深めるということが求められる。
つまり、新しいことを勉強するときに「コンテストに応募する」というインセンティブが生まれるということが重要なのである。「理解しないとコンテストに参加できない」ということが大きな原動力となって、最新技術に対しての理解がより深まっていくということが、まず大事なのではないかと思う。TRONプロジェクトでは、常にイノベーションを起こすことを重要視しているので、コンテストで勝つためには、最新技術に対する知識や理解のうえにイノベーティブな新しい発想を展開できる力が必要になってくる。
たとえば「公共交通オープンデータチャレンジ2024」に約500件という多くの応募があったということは、私達のプロジェクトの目的として望ましいことで、たいへん嬉しく思っている。学生から先端の分野で働く若いエンジニアなども含め、応募してくれた人は非常に多彩であった。私は若い人の応募も大歓迎なので、若い人にはチャレンジする気持ちを忘れないでほしいと思っている。もう一つ私が嬉しかったのは、過去4回の「東京公共交通オープンデータチャレンジ」から、継続して応募してくれた人が何人もいたことだ。「継続は力なり」といわれるように、まったく新しい発想の作品を生み出したり、あるいは前回の作品をブラッシュアップしたりして、何回もチャレンジしてくれる人がいることも、私たちのコンテストの趣旨に沿っている。
また「TRONプログラミングコンテスト2025」の特集では、第1回コンテストの入賞者による手記を掲載している。参加のきっかけや、応募にあたってどういうことに気をつけたのかなど、コンテストを勝ち抜くためのポイントが応募者の視点で書かれていて、コンテストに関心がある方にとってたいへん興味深い内容になっている。
最近米国でトランプ大統領が再任したことにより、今までとは違う原理原則のもとで世界のルールがドラマチックに動こうとしている。そういう激動の世界情勢の中で動いていくうえでも、オープンアーキテクチャの考え方というのはとても大切である。なぜなら、オープンアーキテクチャはその基盤となる技術や仕様が公開されているため、誰もがその詳細を理解し、自らの手で検証し、必要に応じて独自に開発や改良を行うことができるからだ。やはり、何事も自分の頭で考えて自分の力でできるようにしておかなければだめだということを示唆している。逆に言えば、誰かの力を借りないとうまくいかないようなものからの脱却を促す考え方でもある。つまりオープンアーキテクチャは、特定の企業や団体に依存することなく、自律的に技術を活用できる環境を提供することで、結果として「自分の力でできる」という状態を生み出すのである。そのためか、最近TRONプロジェクトに関しての関心が高まっており、問い合わせも増えている。私達も、こうした激変する世界の中でも新しいことを生み出す力が削がれないように、努力していきたいと考えている。
坂村 健

編集後記
最近あるイベントに呼ばれて、生成AIと教育に関する話をしたが、そのとき他の発表者の話を聞いて、いまだに「ハルシネーションに対する注意」をメインに話していたのに驚いた。そのことに驚いたことで、逆に気が付かされたのは、2023年くらいまでは、ちょっとわかった感じの人がAIと言えば「ハルシネーションに気を付けろ」だったのが、最近そういう話をあまり聞かなくなったことだ。そして、そのことを、私自身、普通に感じているということだ。
ハルシネーションはいまだにゼロではないし、注意すべきとも思うが、AIと言えば最初に「ハルシネーションに気を付けろ」というような風潮は、あっという間に過ぎ去ってしまったように思う。もちろん、「AIと言えばハルシネーション」が皆の常識になってしまって、わざわざ誰も言わないということもあるかもしれないが、多分そうではないだろう。
何と言っても大きいのは、普通に使っていて、どんどんハルシネーションが減っているということだ。2022年11月のChatGPT登場のころは、「夏目漱石の主な著作は」と聞くと「源氏物語」とか「我輩は中国人である」とか答えていた。それが今は、ちょっとやそっとでは、そういうあからさまなハルシネーションは起こせない。2022年の11月から今まで、ほんの2年半程度だ。今や、人間の思い込みや知ったかぶりの人より、むしろAIの答えのほうがハルシネーションが少ないぐらいではないだろうか。
当時、「AIはこんなバカな間違いをする」とか、もっと悪意がある人は「AIは嘘をつく」などと言う人もいた。しかし、私は「ハルシネーションを嘘と言うと、AIに悪意があるように錯覚する。ハルシネーションはむしろ、AIが人間の要求に応えようと、知らないことまで推測で補ってしまうために起こるものだ。しかし、AIの学習量が増え、検索で回答の事実確認をするなどの進歩により、ハルシネーションはどんどん減っていくだろう。問題は、AIがハルシネーションを起こすことではない。常に人間の要求に応えようと頑張るAIが、むしろハルシネーションをほとんど起こさなくなったとき、人間がAIに判断まで委ねて責任放棄したくなるという欲求に逆らえるかだ」と、当時から言っていた。
「ハルシネーションに対する注意」をことさらに言う、その久しぶりの時代遅れな発表に接して、逆にその問題がますます現実味を帯びてきたと感じた次第である。
坂村 健
